連合会紹介
会長挨拶

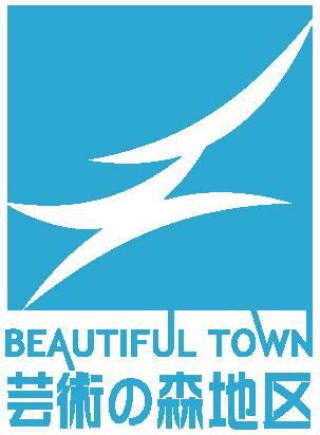
2024年(令和6年)芸術の森地区連合会の活動
2024年度芸術の森地区連合会定期総会は、4月20日(土)芸術の森地区会館で開催し、代議員全員の賛成ですべての議案が承認されました。
本年度もまちづくりビジョン基本理念に沿って事業を行っていきます。
連合会の主な事業、活動の詳細については、地区広報芸術の森59号、60号、61号で報告します。
本年度は、常盤一区町内会とサンブライト真駒内町内会の会長が交代となり、芸術の森地区連合会役員会の一部が改選となりました。芸術の森地区役員名簿をご参照ください。
◇芸術の森地区連合会の経過
2024年度芸術の森地区連合会は、29年目を迎え、まちづくりセンターの自主運営は14年目を迎えます。連合会の構成は、地縁団体見晴町内会、石山東町内会、地縁団体石山八区町内会、常盤団地町内会、常盤一区町内会、真駒内アートパークタウン町内会、サンブライト真駒内町内会、常盤二区町内会、滝野町内会、真駒内三団町内会、真駒内駒岡町内会、駒岡団地町内会の12町内会と芸術の森地区社会福祉協議会、芸術の森地区民生委員・児童委員協議会、芸術の森地区青少年育成委員会、札幌芸術文化財団(芸術の森)、札幌市立大学、札幌市立常盤中学校、札幌市立駒岡小学校、札幌市立芸術の森小学校など地区内に拠点を置く25団体で構成されています。
◇芸術の森地区まちづくりビジョン基本理念
①自ら考え、自ら実践する住民主体のまちづくり ②全世代、全住民が参画する地域自治の実践 ③共に生き、共に行動することを原点に「礼」を重んじた地域社会の確立に向け、連合会活動を展開します。
◇2024年度主な活動
< まちづくり >
・自然、景観 ~雪あかりの祭典、ごみ不法投棄防止擬似鳥居と警告旗設置、撤去
・芸術、文化、スポーツ ~
ソフトボール大会、大運動会、オリエンテーリング大会、文化祭、
G/SMF芸術の森・スクールミュージックフェスティバル、手芸教室、
スマホ教室、青少年育成委員会の行事、
芸術の森スポーツ振興会主催の行事支援、仮称アグリ体験
・福祉活動 ~社会福祉協議会研修会への協力、支え合い活動支援
・広報活動 ~6月、12月、3月に地区広報芸術の森59号、60号、61号発行
< まちおこし >
・花いっぱい運動 ~国道453号沿道花苗植え
・雪あかりの祭典 ~12月初旬から2月下旬、地区内7会場開催の支援
・ヤマメの稚魚放流 ~5月中旬に真駒内川で5,000匹放流
・安全、安心の啓蒙 ~子どもと高齢者の見守り、交通安全推進、春・夏・秋・冬街頭啓発活動
・芸術の森地区の自然を体験~仮称)ホタルの生育環境整備の会、子どもアグリ体験
< 地域各種団体との連携 >
・札幌芸術の森で開催の事業応援、文化祭の開催、G/SMFの開催
・青少年山の家運営協議会、滝野すずらん丘陵公園利用者会議等の参加
・札幌市立大地域環境デザイン学部、学部連携(デザイン学部と看護学部)との交流
・小中学校学習発表会、子どもを見守る会、常盤中ゲストティーチャー等の参加
・芸術の森地区連合会設立30周年事業準備委員会の設立
◇継続事業
- 旧常盤小学校公募提案審査委員会対応
- 国道453号フラワーロードに花を咲かせる会と花苗植え等の対応
- 真駒内川護岸継続事業工事の対応
- 2025年 新駒岡清掃工場稼働に向けた工事等の協力
- 地域内各種関連団体の行事、各種会議への参加など連携した交流
- 各町内会からの要望事項の対応
2024年5月
芸術の森地区連合会 会長 下総 仁志
芸術の森地区連合会役員名簿(PDF)
単位町内会の紹介
地域マップ
社会福祉協議会

「2024年度定期総会報告と事務所の開所」
芸術の森地区社会福祉協議会
会長 塩 田 恒 雄

定期総会は、5月19日((日)14時から芸術の森地区会館で開催(代議員41人:出席者27人、委任状14人)し、来賓の方は、小野寺南区保健福祉部長ほか10人の方が、参加されました。
1 定期報告総会
会長挨拶後、議長(坂下儀弘氏)、議事録署名(田中勇一氏、髙山哲由氏)を選出し、議案審議に入り、事務局から議案第1号(2023年度事業報告)、議案第2号(決算報告)説明後、田渕監事から議案第3号(会計監査報告)の説明があり、一部、第2号決算で質問を受けましたが、承認されました。
議案第4号(2024年度事業計画)は、地区社協事務所移転(もなみ学園多目的室の使用)に伴う事務所及びいこいの広場開設、運営体制の整備、福まちセンター専門部見直しなど、会則等の一部改正と第5号議案(予算案)は、質疑を経て承認されました。
第6号議案(会則及び内規一部・改廃)は、事務所移転(もなみ学園多目的室)、理事会の廃止(見直し)及び第7号議案(役員一部改選)総務部長、会計部長の役員就任等の承認。懇談会が4年振りに開催。
2 主な事業方針
(1)札幌市・社会福祉協議会、地区連合会等の各種会議、研修会の参加
・地区社協三役会、役員会議ほか:毎月1回開催、6月から新事務所(もなみ学園内)
(2)各種補助金事業の申請と適正な執行
ア 福祉のまち推進助成事業
・基本活動事業(福まちセンター運営各部の活動支援)
・地域福祉あんしん事推進事業(福祉マップ等)
・ふれあい交流事業・基本活動強化事業(見守り体制整備、世帯名簿と活動記録表の整備)
イ 共同募金地域福祉推進事業(地区社協事務所開設に伴う広報啓発)
(3) 地区社会福祉協議会の運営・体制等の整備
地区社協事務所開所と「いこいの広場」開設(※詳細は、掲載)
(4)各町内会福祉組織及び各団体への助成金見直し
(5)地区福祉のまち推進センター運営委員会の事業計画
地区社協の活動体として、各専門部により下記の事業計画の実施に向け、センター委員等の協力を得て、定例会議(年4回)開催し、活動の推進を図ります。
特に、運営委員会を新たに設置し、昨年度まで生活支援部が担当していた、福祉推進員・協力員対象の研修会・全地域住民対象の講演会、調査研修部が担当していた講演会・調査事業等の企画運営を担当することにより、より多くの情報を元に事業実施が期待できると考えます。
活発な意見交換により、福祉に関する情報提供や体験の機会を提供しその知識を共有していきます。
事務所の活用として、気軽に誰でも集える居場所・交流の場を提供することで、地域の声を聞く場にも繋がる事が期待され、各単町センター委員との年間4回の委員会では、単町の活動支援に向けて情報交換を行い、連携を強化していきます。
各事業担当部長を中心に、センター委員、福祉推進員と知恵を出し合い、力を合わせて、地域の皆ささまが楽しく参加できる事業の充実・強化に努めます。
(5)広報・啓発活動の充実(地区社協福まちだよりー絆―、地区広報芸術の森の協力、ホームページ)
(6)学校教育との連携(小学校、中学校、大学等)
(7)5月からコロナの感染症法上の位置づけが「5類」に引き下げられますが、事業取組みは、北海道等の通知により感染予防に努め、活動の推進を図ります。
3 地域共生社会をめざして
札幌市社会福祉協議会(以下「市社協」)は、令和6年度「第6次さっぽろ市民福祉活動計画」(6年間)の活動指針を策定し、基本理念「住み慣れた地域で、みんなが主体的に参加し、つながり、支え合って暮らせるやさしいまち」により地域での助け合い活動及び人との結びつき活動の担い手の拡充に努め、福祉の推進に向けた取り組みが図られます。
当地区社協は、本活動計画に基づき、札幌市、市社協、地区連合会、地区民生委員児童委員協議会ほか関係団体等と連携し、地域福祉の向上に努めてまいります。
なお、本年度は、地区社協体制、事業の円滑化を図るため、「事務所移転」「福まちセンター専門部見直し」など「会則等の一部改正」を行い、活動を推進いたします。
| ☆芸術の森地区社会福祉協議会事務所移転と「いこいの広場」の開設! 6月3日から、もなみ学園(旧石山東小学校跡地)内に、地区社会福祉協議会事務所を開所しました。 なお、6月4日から、どなたでも集える「いこいの広場」を開設しましたので、お気軽にご利用ください。 ☆場所: 札幌市南区石山東5丁目6-1(もなみ学園内) 芸術の森地区社会福祉協議会事務所 電話・FAX:011-592-5343 ☆ご利用方法・日時: 毎週火・木曜日の午前9時30分~12時まで(祝日・年末年始は除きます) 地域の方々のお話相手、軽い運動、お困りごとなどボランテイアが専門機関と連携し、支え合い楽しい 場としてご利用ができます。 |
芸術の森地区民生委員・児童委員協議会
| 創立 | 委員数 | 会長 |
| 1995年(平成7年) | 定員18人(現在16人、欠員2人) | 下総 仁志 2019年(令和元年12月~) |

紹 介
芸術の森地区民生委員・児童委員協議会は、国道453号線、真駒内滝野線及び道道真駒内御料札幌線沿いに位置し、真駒内川、精進川、厚別川のせせらぎと自然豊かな緑に囲まれた地域にお住いの方を担当しています。
1995年(平成7年)4月に石山町内会連合会から分割して、芸術の森地区連合会が発足したのを機に芸術の森地区民生委員・児童委員協議会(以下、地区民児協と言う)が発足し、2023年度で28年目となります。
現在、民生委員・児童委員(定数16人)14人、主任児童委員(定数2人)2人の合計16人(欠員2人)で活動しています。
2022年12月一斉改選で民生委員・児童委員の担当区域(真駒内アートパークタウン町内会と石山東町内会)でそれぞれ1人の欠員となりました。欠員区域は、現在同じ町内会の民生委員・児童委員が代行しています。欠員区域にお住まいの方で民生委員・児童委員活動に、ご理解・ご協力いただける方、興味のある方、民生委員・児童委員として募集しています。 民生委員児童委員協議会 会長 下総 仁志(携帯電話090-9088-1010)までご連絡をお願い致します。
民生委員・児童委員、主任児童委員の主な活動
◆今、民生委員に求められている役割とは
◇調査活動:地域に散らばるアンテナとしての役割
◇相談・援助活動:専門機関や専門職につなぐ役割
◇必要な情報の提供:住民や関係機関と協働する役割
◇関係行政機関の業務に対する協力:代弁者としての役割
◇新たなサービスを開拓する役割
◇社会福祉施設との連携等:福祉の理解を広める、まちづくりの推進者としての役割
◆民生委員・児童委員、主任児童委員(以下民生委員という)は、地域住民の立場にたって地域の福祉を担うボランティアです。
民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。
また、民生委員は児童福祉法に定める児童委員を兼ねています。
ボランティアとして活動して給与の支給はありません。任期は3年です。
◎民生委員・児童委員とは
◇地域を見守り、地域住民の身近な相談相手、専門機関へのつなぎ役です。
自らも地域住民の一員として、担当区域において高齢者や障がいのある方の安否確認や見守り、子供たちへの声かけ等を行っています。
医療や介護の悩み、妊娠や子育ての不安、失業や経済的困窮による生活上の心配ごとなど、色々な相談に応じます。 相談内容に応じて、必要な支援が受けられるよう、地域の専門機関とのつなぎ役になります。
◎主任児童委員とは
◇子育てを社会全体で支える「健やかに子供を産み育てる環境づくり」を進めるために、平成6年1月に制度化されました。
◇子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員です。
◇主任児童委員は、担当区域を持たず、区域担当の民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。
芸術の森地区青少年育成委員会
ご挨拶
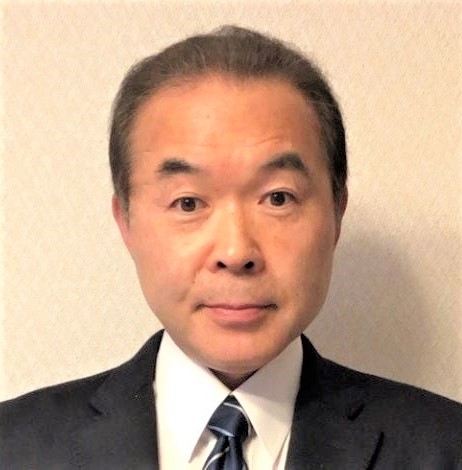

~青少年育成委員会の紹介と今年度の取組み~
青少年育成委員会 会長 松原 義雄
札幌市青少年育成委員会は地域において子どもたちの健全な育成に関する実践活動を推進するため、市内90地区(連合町内会単位)に組織されています。市長から選任を受けた委員(任期3年)がスポーツ、文化事業や環境対策事業などさまざまな事業を実施しています。南区内は10地区、150人ほどの委員定数で、芸術の森地区では15人の委員が2年目の活動をスタートしました。
今年度は新規事業を含め子どもたちが参加する4事業の活動を以下の通り計画しております。
1 こどもアグリ体験
今年度新規に芸術の森地区連合会と共同開催事業で子どもたちに農業体験をしてもらうイベント。春にじゃがいもの種を植え、生育過程を観察しながら秋の収穫時期に収穫したいもを調理して食する食育活動の一環事業です。すでに5月11日(土)に作付けを終了し収穫は9月下旬に行う予定です。収穫時期になりましたら地域の皆さんにお知らせしますで多数の参加をお待ちしております。
2 施設見学会
4月にリニューアルオープンした青少年科学館の見学会を10月下旬に予定しております。子どもたちが楽しみながら色々学ぶことで科学への興味・関心を持ってもらえれば幸いです。
3 餅つき大会
12月に開催予定で餅つきを通して地域の子どもたちとふれあい、餅つき文化の継承を図って行きたいと思います。
4 初心者スキー教室
1月~2月開催予定しています。スキーの楽しさとレベルアップを目的とした小学生対象のスキー講習会です。
その他、連合会及び学校関連行事の参加、また各町内会イベント等にも積極的に参加して子どもたちとの触れ合う機会を多く持ちたいと思っております。
また、当委員会は今年度から2人の高校生を含む組織となり全市的に見ても年齢層が一番若い委員会であると思います。今後の活動の中で2人を温かく見守り、時には若いパワーをもらって今年度も子どもたちが楽しく参加できる事業を委員一同チームワーク良く取り組んで行きますので、これからも地域の皆様にはご支援とご協力をお願いいたします。
芸術の森地区育成委員名簿(PDF)
芸術の森地区 広報誌
地区広報 芸術の森 (創立20周年記念誌を含む)
「地区広報 芸術の森」は、平成16年7月
芸術の森地区町内会連合会(現地区連合会)広報「やませみ」
〃 社会福祉協議会・福祉のまち推進センター 広報「ばんけいぬま」
〃 青少年育成委員会 広報「森のこえ」
の三者の賛同を得、これを中核とし地域を網羅する総合広報紙として、装いを新たに刊行されたものです。
現在、地区連合会、地区社会福祉協議会、地区青少年育成委員会などから編集委員会を構成し、年3回の定期号(各8~10ページ)のほか、必要に応じてお知らせ特集号(2~4ページ)を発行しております。
「統合」は、「(機能を高めるために)一つのまとまりのあるものにする」とあります。今後とも初心に立ち返り、「知りたい情報をわかり易く発信する」「紙面をとおし意見交換・交流の場とする」ことを、都度々々に再認識し、取材・編集に努めてまいりたいと考えております。
これまで同様ご意見をお寄せいただき、ご投稿ご協力をお願い致します。

